うつ・ストレス対策は「腸」から!免疫力を高め心を整える食物繊維の力が体調を整えてくれます。「最近、気分が晴れない」「ストレスでお腹の調子が悪い」……。そんな悩みを抱えている方は、もしかすると「腸」からの SOS を受け取っているのかもしれません。
うつ・ストレス対策は「腸」から!免疫力を高め心を整える食物繊維の力
かつて、脳のない生物であるヒドラなどの腔腸動物が「腸」だけで生きていたように、腸は「第二の脳」と呼ばれるほど、私たちの精神状態と密接に関わっています。実は、心を穏やかに保つ「幸せ物質」セロトニンの生成には、腸内細菌の働きが欠かせないことが分かってきました。
本記事では、脳と腸が影響し合う「脳腸相関」の仕組みを紐解きながら、なぜ食物繊維を摂ることがメンタルヘルスに良い影響を与えるのか、その驚きのメカニズムを解説します。
ストレス社会に負けない健やかな心を取り戻すための、食事と腸内環境の整え方を見ていきましょう。
脳のストレスは腸に影響する
地球上には、脳がない生物は多数います。腔腸動物がそうです。それでは、彼らはどこから指令を受けて、行動しているのでしょうか。それは腸なのです。ヒドラのような生き物を観察していると、膿が脳の原型であることがよくわかります。
腔腸動物から進化してきた人間の腸にはたくさんの神経叢が集中しています。これは、ほかの臓器には見られない特徴で、腸が「第二の脳」と呼ぼれる所以です。だから、強いストレスを受けると、心にダメージを受けると同時に、お腹の具合も悪くなるのです。
「今日は学校に行きたくない」「会社に行きたくない」などの日に下痢をしてしまった経験は誰にもあるはずです。
実際、ストレスに満ちた現代社会では、検査しても異常がないのに、下痢や便秘を繰り返す便通異常の人が増えています。「過敏性腸症候群」とか「機能性便秘」、さらには出勤途中の電車で駅に着くたびにトイレに駆け込む「各駅停車症候群」といった腸障害は、21世紀になって急増しているのです。
日本語には「腸が煮えくり返る」とか「腹が立つ」「腹が据わる」「腹に据えかねる」「腹に落ちる」「腹に据えかねる」「腹を決める」「腹を探る」など、「腹」のつく表現がたくさんあります。それも、脳(=心) と腸(=腹) とが繋がっていることの表れです。
腸内細菌は脳に「幸せ物質」を運んでいた!
下痢や便秘は多くの場合、強いストレスが加わることによって、自律神経のバランスをくずし、腸管の運動が乱れることが原因で起こります。便通異常を起こすと、腸内細菌が減少することもわかっています。それも、善玉菌が著しく減っていくのです。
免疫反応は大腸に棲む腸内細菌の数や種類が決めていますから、腸内細菌が減少すると当然免疫力は低下します。
逆に、ストレスがない状況では、便通異常は起こらないし、腸内紳菌のバランスも保たれて、健康でいられます。腸内細菌のバランスが良ければ、免疫力が上がってストレス耐性が強くなる、という見方もできます。
つまり、ストレスと腸管運動、免疫反応は、トライアングルのように連携して、心身の健康にいい意味でも悪い意味でも循環をもたらすわけです。
そこで重要になってくるのが、免疫力を上げることです。その免疫力は「70%が腸管の働きで、残リ30%は心で決まる」ときれています。
腸が喜ぶにはまず、腸内細菌が喜ぶものを食べることがポイントになります。抗菌剤や防腐剤などが使われている「人工的な食べ物」を極力避けて、日本の伝統食に象徴される食事をするのがベストでしょう。
あと「30% が心」ですが、この部分でも腸内細菌は貢献しています。腸内細菌は「幸せ物質」を脳に運ぶからです。
たとえば、最近増えている「うつ」の原因の1つは、脳のなかのセロトニンという「幸せ物質」が不足していることです。
このセロトニンのもとになるのは、トリプトファンというアミノ酸です。栄養学者などが、「うつを改善するために、肉や魚、大豆、ピーナッツ、乳製品など、トリプトファンを豊富に含む食品を食べなさい」と口にしますがそのとおりなのです。
ただし、いくらトリプトファンを摂取しても、それをきちんと分解して吸収できるようにしてくれる腸内細菌がいないと脳に送られません。腸内細菌が心の部分でも非常に重要だ、ということです。
うつとアレルギーは同時に増える
現代人は腸内最近が少ないことからアトピーなどのアレルギーになる人が増えてきました。それと同じことが、うつ病にもいえます。ここ10年で、有病率が2倍以上になっているのは、アトピーやぜんそくなどのアレルギー性疾患とうつ病なのです。アレルギー性疾患とうつ病とは同じような増加曲線を措いています。その大きな原因の1つはやはり、腸内細菌が減ってきたことにあると思います。
こんな仮説はどうでしょうか?
「自殺率の低い国の人たちは、食物繊維をたっぷり摂っている」
実際にメキシコは自殺率が非常に低い国ですが、世界で最も食物繊維を摂っている国としても有名です。
自殺の原因としてよく、「経済的に追い詰められる」ことが指摘されていますが、メキシコは貧しい国です。それでも自殺者が少ないのは、食物繊維が豊富なトウモロコシや豆をたくさん食べているからではないでしょうか。
便秘で困ったらオススメの特定保健用食品【イサゴール】を試す!
つまり、メキシコ人は腸内紳菌を豊富に持っていて、その腸内細菌が脳に「幸せ物質」を運んでいるから、経済的に困窮するなどの状況があっても、たくましく生きていけるのではないでそうか?
食物繊維を摂ることは、野菜や豆類など植物性の食品をたくさん食べれぼいいだけですから、そう難しくはありません。「うつ」などの心の病気を予防するには、食物繊維をたっぷり摂って、腸内細菌から解決していくのも1つの方法ではないでしょうか。
ぽかぽかの体でうつを治すでは体を温めることでうつを改善するものですが、体を温めることもとても重要です。
まとめ
私たちの心と体は「脳腸相関」という強い絆で結ばれています。「第二の脳」とも呼ばれる腸は、単なる消化器官ではなく、自律神経や免疫システム、さらには精神状態までをも左右する重要な司令塔です。
現代社会において、うつ病やアレルギー疾患が急増している背景には、加工食品の摂取増加やストレスによる腸内細菌の減少が深く関わっています。心を穏やかに保つ「幸せ物質」セロトニンを脳へ届けるためには、その原料となる栄養素を分解・吸収してくれる健やかな腸内細菌の存在が欠かせません。
ストレスに負けない心を作る第一歩は、腸内細菌のエサとなる食物繊維をたっぷりと摂り、日本の伝統食のような「腸が喜ぶ食事」を意識することです。腸内環境を整えることは、免疫力を高めるだけでなく、内側から「幸せ」を感じやすい体質へと導いてくれます。日々の食事を通じて腸を労わり、心身ともに健やかな毎日を目指しましょう。
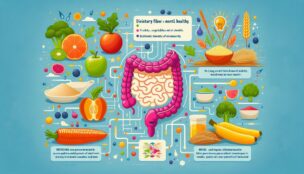

最近のコメント