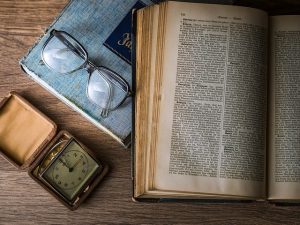朝食 重要性 ぜん動運動 を促すためとても重要です。朝食の重要性はさまざまですが、大腸が動く ぜん動運動 のきっかけになりますので、便秘解消のためには朝食は重要です。胃に食べた物が入ると、大腸の横行結腸からのS状結腸にかけて急激なぜん動運動が起こります。これが胃・結腸反応と呼ばれるものです。
朝食 重要性 ためのぜん動運動 のためにも朝食はしっかり食べる
 朝食 重要性
朝食 重要性
食べ物が胃に入るととぜん動運動が起きる
胃に食べた物が入ると、大腸の横行結腸からのS状結腸にかけて急激なぜん動運動が起こります。これが胃・結腸反応と呼ばれるものです。
ぜん動運動 というのは、腸管の口側が収縮(せばまる)し、肛門側が弛緩(広がる)して内容物を先へ押し出していく運動のことで、主に腸の内容物を移動させる働きを言います。
その ぜん動運動 によって、小腸にあった流動性の消化物は結腸に押し出され、大腸へ移動します。そこでさらに水分が吸収され、直腸に送り込まれると自律神経の働きによって便意を感じることができるのです。それは 3 ~ 4 回断続的に起こり、1 日のうちに 1 ~ 2 回起こるとされています。この胃・結腸反射が最も起こりやすいのは、朝食後です。
なぜなら、逆に食べた食事から最も長く時間が経過しており、胃がからっぽになっているためです。便秘傾向の人は、ともかく朝食をしっかりた食べて排泄を促します。ダイエットなどといって朝食をぬいていたら便秘になってしまいダイエットにもなりません。
腸のぜん動運動で便意を感じたらすぐトイレに
また朝食の後に大切なのは、便意に素直に従い、トイレに行くことです。便意は結腸にためられていた便の元が直腸へと移動したときに、直腸壁のセンサーが大脳に送られることによって「便意」を感じることができます。その便意を我慢してしまうと、大腸内のセンサーが麻痺し、そうのうち便意そのものを感じなくなってしまうのです。
規則正しい食事の中でも ぜん動運動に欠かせないのが 朝食 ということになります。日頃の食事では善玉菌を増やすのに役立つ発酵食品と、善玉菌のエサとなる食物繊維を多く含む野菜や果物、きのこ類、海藻類を積極的にいただきましょう。
毎日は負担が大きいという人は、食事の〝置き換え〟がおすすめです。ほんの少しの工夫で、効率よく摂ることができます。
また硬い便に困っている人はオクラやもずく、なめこ、山芋などのヌルヌル食材を多めに摂りましょう。水溶性食物繊維が多く含まれているため、便を軟らかくするのに有効です。
朝食の重要性
「大腸の蠕動運動を促す反応」を高めることも大切です。元々人間には、「ご飯を食べると腸が動く」という神経反応があります。これを「胃・結腸反射」といい、一日のいつでも起こりますが、この反射が一番強く大きく起こるのが朝である、ということが分かっています。ですから、便秘の人は、朝食をしっかり食べるということがとても大切なのです。
ぜん動運動 リラックス 状態で
もうひとつ、腸が良く動く条件として、身体がリラックス状態にあることが重要です。朝、ぎりごりまで寝ていて、そのままま仕事や学校に飛び出している人は、リラックス状態ではなくむしろ緊張状態といえるでしょう。朝は、時間に余裕をもって起き、ゆったりと朝食を食べることがとても大切です。ぜん動運動を起こすためにも緊張状態はNGです。
身体は、緊張状態にあると、何があってもすぐに対処できるよう血液を脳や筋肉にまわします。このため、消化吸収するお腹への血流は減少するのです。逆に、リラックス状態にあると、エネルギーを得るために消化吸収の働き高めるようお腹への血流が増え、腸が良く動くようになります。 緊張するとお腹が痛くなって下痢をしたり、ストレスがたまっていると逆に便秘になったりといったことは誰しもが経験したことがあるでしょう。 土日だけは良い排便なのに、平日はずっと下痢か便秘、またはコロコロ便、という人も珍しくはありません。
善玉菌を増やす
にがり 1 日に70 mg マグネシウムが便秘解消に効果