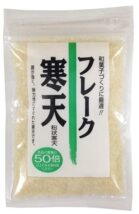寒天 効果 を上手に活用する方法を紹介します。ご飯 やみそ汁にも入れて腸内環境を改善しましょう。ご飯 にも入れて食物繊維 摂る みそ汁にも入れて活用食物繊維 摂る みそ汁にも入れて活用できます。寒天 ご飯やみそ汁にも入れて活用 すると腸活に最適です。寒天の材料は海藻の仲間のてんぐさ。ほかの海藻同様に 水溶性食物繊維 が豊富に含まれています。食物繊維 たっぷりの寒天をご飯やみそ汁にも入れれば食物繊維をたっぷり摂ることができます。
寒天 効果 人気が急上昇
寒天は海藻の食物繊維をたくさん含んでいるのでおなかの調子を整えてお通じを改善します。 寒天の食物繊維には腸から吸収されずに便の材料となるため便の量が増えて、おなかがスッキリします。
寒天(粉)100g中に含まれる食物繊維の量は79g(角寒天では74.1g)。その含有量は、あらゆる食品のなかでもベスト3に入る量です。
食物繊維には、よく知られているお腹の調子を整える効果のほかに、糖の吸収を抑えたり、コレステロールを体外に排出する作用があります。便秘や軟便など、お腹の調子に悩んでいる方や、ダイエット中の方もぜひ積極的にとりたい成分です。全体量のおよそ70〜80%が食物繊維である寒天は、効率よく食物繊維をとるのにピッタリの食材です。

寒天の材料は海藻の仲間のてんぐさ。ほかの海藻同様に水溶性食物繊維が豊富に含まれています。ですから、寒天を常食すると、腸内で水分を含んだ、ほどよい柔らかさの便をつくります。
また、腸だけでなく、水溶性特有の性質が、胆汁酸や余分な脂肪酸やコレステロールを吸着してカラダの外へ排泄する働きもあり、生活習慣病を予防することにもつながります。さらに糖質の吸収を抑えるためダイエットにも効果があります。
寒天 味
「寒天」の特徴とは?
・味:ほぼ無味で味への影響は少ない。 天然寒天は海藻が香る場合もある。
・特徴:ゼラチンに比べ、強度がある。
味がないのでどんな料理にも加えて食物繊維が摂れるのがとても使いやすいです。寒天 効果 を得やすいのでおすすめです。また、寒天を使ったものもたくさん売られています。
寒天 栄養
寒天 には食物繊維の他にもカルシウム、鉄、カリウムなどが含まれています。
寒天の生理機能 寒天に豊富に含まれる食物繊維が、様々な生理機能を発揮します。 排便を促して便秘を解消したり、コレステロールの吸収を防ぐ効果が良く知られています。
おやつだけではもったいない ごはんやみそ汁にも
ちろん寒天ゼリーやところてんにも食物繊維が含まれているので、食物繊維がもたらす寒天の効果はあるでしょう。しかし、ゼリーやところてんに調理した状態では一食分に使われている寒天の量はわずかで、寒天ゼリー1つの食物繊維量はおよそ0.2g、ところてん1人前で0.8g程度と、多くの食物繊維が摂れるわけではありません。寒天 効果 の期待は薄いかもしれません。
ゼリーや和菓子などでお馴染みの寒天ですが、ところてんをおやつにもするのもよいのですが、おやつだけではたいした量を摂取することができません
棒寒天をご飯に入れて炊き込んだり、みそ汁に入れて飲んでしまう方法がおすすめです。
棒寒天を水でもどし、小さくちぎってご飯と一緒に炊くと、もちっとした食感を楽しむことができます。ごはんを3食食べる人は、これで食物繊維が十分摂れます。ダイエット中の便秘対策にも利用できます。朝のコーヒーに入れるのもいいでしょう。
ちぎった寒天をみそ汁やスープに入れて食べるのもおいしいです。ふかふれのような食感が味わえます。粉寒天ならみそ汁だけでなく、お茶やコーヒーに入れても味が変わることなく手軽に寒天が食べられます。
寒天 注意 脱水症状
寒天は体内で 250 倍もの水分を吸収する力があります。手軽だからと一度にたくさんの寒天を摂ると、体内の必要な水分まで吸収してしまい、脱水症状になってしまうことさえあります。ご飯なら 1 合に 4 分の 1 本くらい、粉末なら 1 食ティースプーンすりきり1杯程度を目安に少量ずつ続けるのがいいでしょう。
また、寒天 は40℃位で固まり始めます。 寒天液と冷たい液体を合わせる際は冷たい液体を人肌に温めてから寒天液に加えてください。 温度差があると均一に固まらない場合があります。 また、酸味の強い果汁と一緒に煮立てると固まらなくなる場合がありますので、加える際は火を止めてから加えてください。
食物繊維摂取のために寒天を使うメリット
1. 食物繊維が豊富(特に水溶性食物繊維)
寒天は ほぼ100%が食物繊維 で構成されており、特に水溶性食物繊維が豊富です。これにより、腸内環境を整え、便通をスムーズにする 効果が期待できます。
2. 低カロリーでダイエットに最適
寒天はカロリーがほぼゼロ(100gあたり約3kcal)なので、ダイエット中でも安心して摂取できます。食べると満腹感を得やすく、食べ過ぎ防止にも役立ちます。
3. 血糖値の上昇を抑える
水溶性食物繊維には、糖質の吸収を緩やかにする働きがあり、食後の血糖値の急激な上昇を抑える 効果が期待できます。糖尿病や血糖値管理をしたい人にもおすすめです。
4. コレステロールや脂質の吸収を抑える
寒天に含まれる食物繊維が、余分なコレステロールや脂質を吸着し、排出を促す 働きがあります。これにより、生活習慣病の予防 にもつながります。
5. 手軽に取り入れやすい
寒天は ゼリー、スープ、味噌汁、煮物、ジュース などに簡単に加えられ、食生活に取り入れやすいのもメリットです。
6. 腸内環境を整え、便秘解消をサポート
寒天は腸で水分を吸収しながら膨らみ、便のかさを増して腸のぜん動運動を促進 します。これにより、自然な排便をサポートし、便秘解消に役立ちます。
寒天の摂取ポイント
- 水分をしっかり取ると、よりスムーズな排便につながる
- 1日 2g〜5g 程度を目安に摂取するのが理想的
寒天は、健康維持・ダイエット・腸活におすすめの食材です!
寒天が苦手なら イサゴール で食物繊維を
[PR]
フレーク状ですぐに使える コシが強く、弾力性に優れた寒天です
☆みつ豆・水ようかん・寒天寄せなどに
1.本品5gを水または、ぬるま湯(約400ml~450ml)につけてやわらかくなるまでもどします。
目安:水・・・約3時間以上 ぬるま湯・・・約1時間
2.火にかけ沸騰後、弱火で約5分~10分(冬場)混ぜながら煮溶かし、味をつける等して型に
流し込み冷やし固めます。
☆炊飯に
洗米後に本品を混ぜ、通常通りの水加減で炊飯してください。
つやと粘りのあるご飯に仕上がります。
目安:3合(3カップ)のお米に対して、本品小さじ1杯程度
栄養成分
| エネルギー | 158kcal |
| たんぱく質 | 1.7g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 76.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |